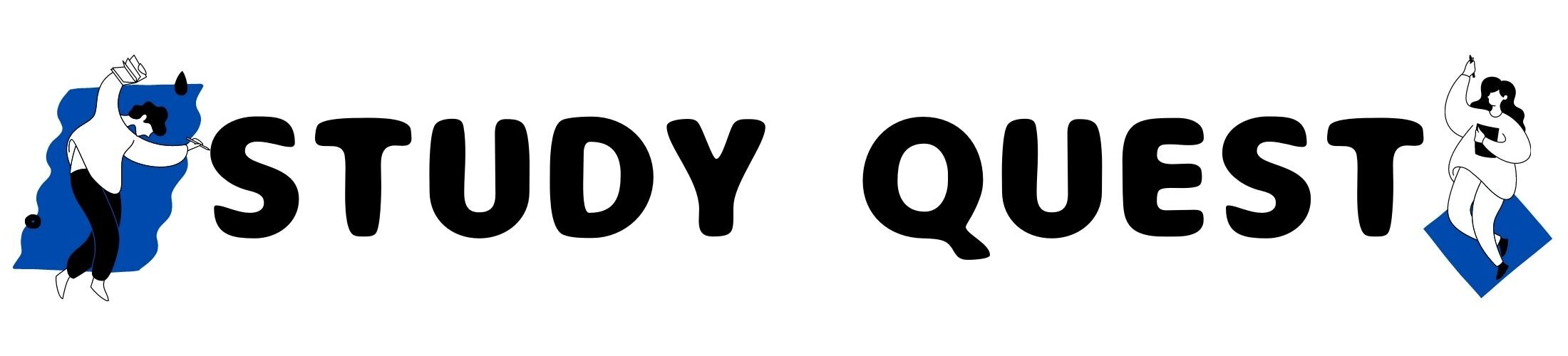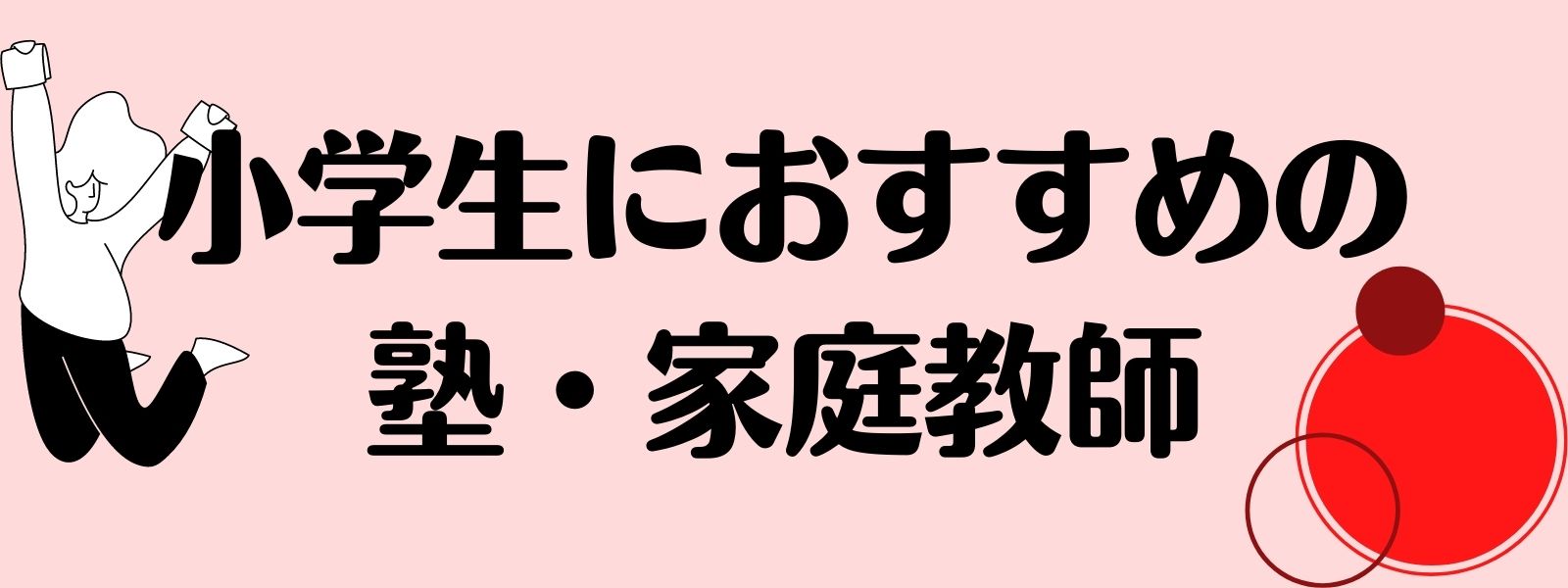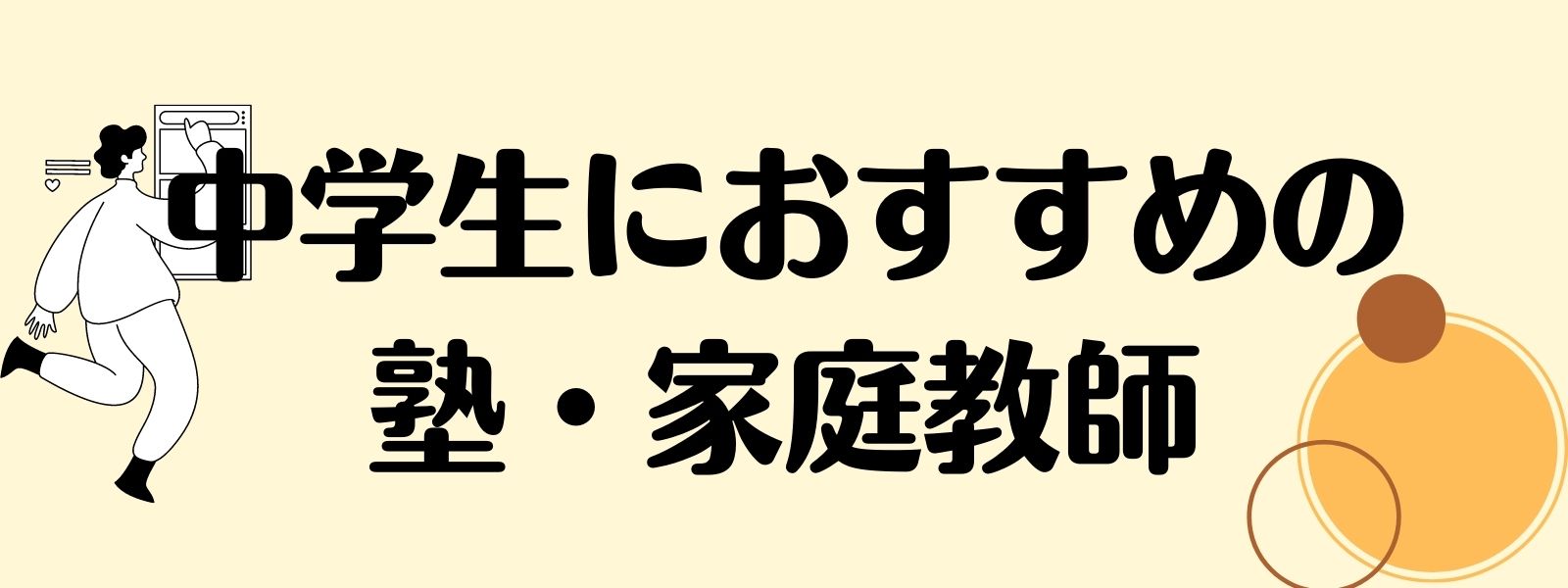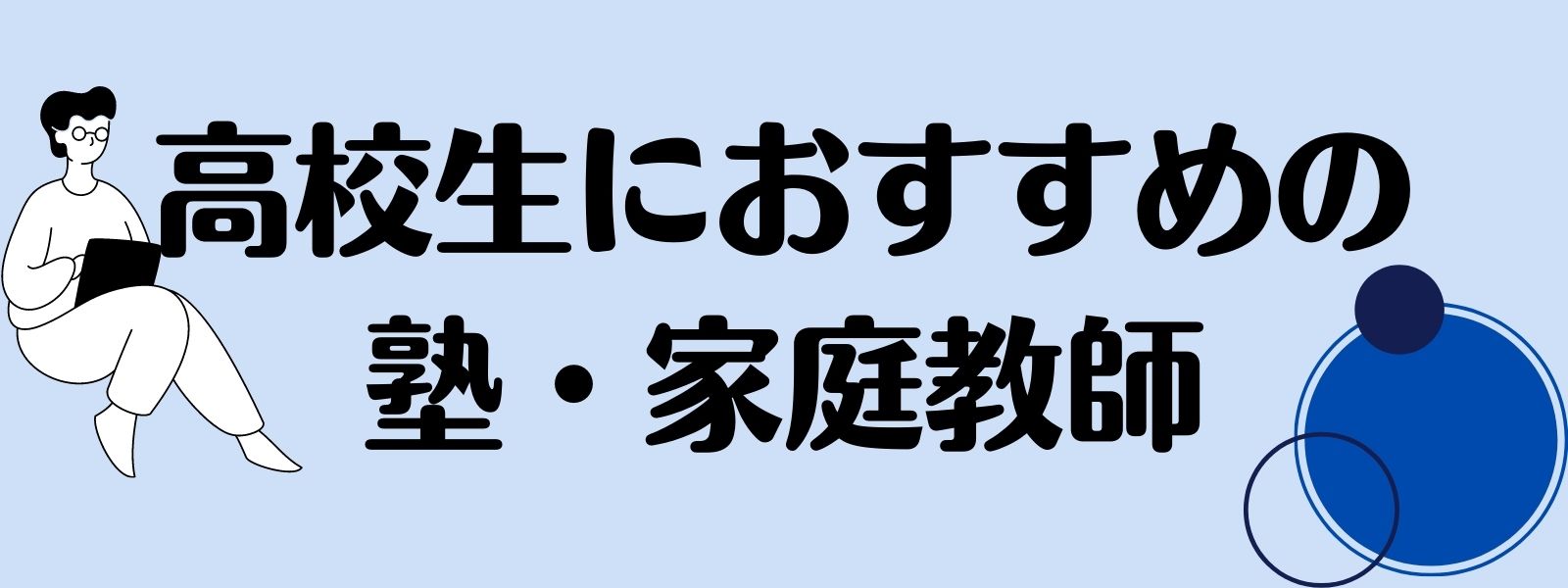このように考えている人のための記事になります。
今回は、『古文の効率的な勉強法』を解説していきます。
古文は文系にも理系にも必要になる教科ですよね。正直、感覚や雰囲気で解いてきた人もたくさんいるでしょう。
そんな人は問題によって解けたり解けなかったりして、受験本番大丈夫なのか不安があるのではないでしょうか?
僕は古文が全く好きではありませんでした。でも自分で勉強法を確立したことで、古文に対する理解を深められました。
その経験をもとにどうやって勉強したら効率的に古文の成績を上げていけるのか、詳しくまとめました。
ぜひ最後まで読んでください。
また、動画でも解説していますのでこちらも見てみてください。
それでは早速いきましょう。
古文は外国語の気持ちで
「古文は昔の日本語だから雰囲気、感覚でできるっしょ」と考えている人。とても危険です。
たしかに昔の日本語であることは間違いありません。ですが、それだと問題によって解ける/解けないが出てきてしまいます。
もし雰囲気や感覚で出来ない問題が本番出題されたら撃沈します。
そもそも雰囲気で読めるものを出題なんてしてくれませんし、問われる箇所は正確に読めているかを試すところばかりです。
雰囲気や感覚では通用しないので、古文を勉強する時は、外国を習う気持ちでいてください。
例えば英語を勉強する時は、単語、文法、発音…など、基礎から徹底的にやっていきますよね。
古文もこのように勉強を進めていくことが大切です。
古文の勉強法~必要な5つの力~
古文の攻略に必要な力はこの5つです。
- 単語
- 文法
- 時代背景
- 読解
- 解き方
特に単語と文法、ここの学習をサボってはいけません。
古文は基礎固めから
どの教科でもい言えることですが古文は基礎が大事です。その基礎が「単語」と「文法」の2つになります。
この2つが中途半端になっていると文を正しく読めなくなります。そして結果的に「こんな感じかな?」という感覚で読むことになり、解答が導けなくなります。
あなたは単語、文法をすべて完璧に覚えていると言う自信はありますか?1年生の初めにばーっとやって曖昧になってませんか?
古文は覚えることがたくさんあり正直めんどくさいですが、覚えてしまえば後はそれを上手に引き出せるようにするだけ得点が狙える教科です。
最初はとにかく大変だけど、この基礎固めを徹底してください。
古文の勉強法①単語
まずは、単語について解説していきます。
単語の重要性
単語は古文を正しく読んでいく上で、非常に大事になります。正しい意味を覚えましょう。
注意しないといけないのは、現代の日本語とは意味が違うものがたくさんあることです。
なんとなく分かる、という状態にはしないようにしてください。
単語が全てではありませんが、単語が分からなければ何も始まりません。
さらに単語を知っているだけで正誤問題5つの選択肢のうちの2つを消すことができたりします。
文の理解、正答率のアップのためにも単語力は上げましょう。
300語ほど載っている単語帳で十分です。英単語と比べて圧倒的に量が少ないのでさくっと覚えましょう。
単語の覚え方
覚え方は自分に合うように工夫しましょう。おすすめなのは、「声に出す」「語源を覚える」「語呂で覚える」「例文と覚える」です。
あなたに合う方法を選んで覚えていきましょう。
また覚える時は複数の意味を覚えましょう。古文単語には複数の意味を持つものがあり、文の中でどれが使われるかわかりません。
だから単語帳に書かれている言葉の意味はすべて覚えておくといいです。
古文の勉強法②文法
基礎の2つ目が文法です。これが最もめんどくさいですが、完璧にしたら古文が読みやすくて仕方なくなります。
文の意味が分かりやすくなるので文法は何としても完璧に覚えることをおすすめします。
文法と言いましたが、この中身は幅が広いです。動詞、助動詞、形容詞、形容動詞、助詞、敬語…
細かくは書きませんが本当に幅広く、途中で覚えるのが嫌になってしまった人もいるでしょう。
だけど、文法ができなければ古文は本当に読めません。必ず覚えて文を見た時に瞬時に判断できるようにしてください。
古典文法の最初と最後のページに詳しくまとめられた表があります。その表を全て覚えることを目指しましょう。
それぞれどういうことを覚えるべきなのかここにまとめていきます。
動詞、形容詞、形容動詞
動詞、形容詞、形容動詞は活用の種類と活用形を覚えましょう。
覚えること(例)
- 動詞⇒四段活用の連用形
- 形容詞⇒ク活用の未然形
- 形容動詞⇒ナリ活用の已然形 など
このようになります。
ポイントは活用の種類が少ないものは早めに覚えてしまうことです。
上一段活用は「ひいきにみゐ」、下一段活用は「蹴る」はこれしかないのですっと出てくるようにしましょう。
助動詞
助動詞は活用表を丸暗記してください。多くて大変ですがこれが1番です。
具体的に何を覚えたらいいのかというと意味、種類、活用形、接続です。
覚えること(例)
- 推量の助動詞,「む」,終止形,未然形接続 など
といった感じです。
これが動詞と混ざってしまい、ごちゃごちゃする人も多いでしょう。だから文に出てきたときは品詞分解をして判断するようにしてください。
落ち着いてやれば確実にできます。
助動詞の種類の判断
助動詞の種類を判断する時には、接続が大きなヒントになります。
例えば「ぬ」という助動詞の場合。「ぬ」は打消と完了があります。
例えば「参りぬ」の場合。この「ぬ」は「参る」というラ行四段活用の動詞の連用形に接続されています。動詞の連用形に接続されているということはこの「ぬ」は完了の「ぬ」だと判断できます。
助動詞の意味の判別
意味の多い助動詞は判別方法も覚えていきましょう。例えば自発、可能、受身、尊敬という4つの意味を持つ「る・らる」
| 助動詞「る・らる」の判別方法 | |
| 組み合わせ | 意味 |
| 「知覚動詞」+「る・らる」 | 自発 |
| 「打消し・反語」+「る・らる」 | 可能 |
| 「受身の相手+に」+「る・らる」 | 受身 |
| 「身分の高い人の動作」+「る・らる」 | 尊敬 |
すべてこれでできるとは限りませんが、判別できるものは判別したほうが文章が読みやすくなります。
接続助詞
接続助詞は「~ば」「~ども」などです。
基本は順接、逆接、単純接続で意味はそこまで多くありませんが、主語が変わる/変わらないのポイントになる重要な役割を果たしています。
サボらずに徹底的にやりましょう。
敬語
敬語は丁寧、尊敬、謙譲の3種類です。敬語が分かることでその動作の主語が誰になるのかが判断できます。
古文で内容が分からなくなってしまう理由は主語が書かれておらず、誰の動作かが分からなくなってしまうからです。
それを防止してくれるのが敬語になります。
また動作の主が分かればいいわけではなく、誰から誰への敬意なのかも分かるとより文の理解が深まります。
文法のまとめ
さて文法について色々話しましたが、これが全てではありません。係り結びや格助詞、副助詞などもあります。
「覚えることがたくさんあってめんどくさい」というのが本音でしょう。
でも、これをできるかできないかが結果に大きく関わってきます。
全国の受験生がサボってしまうようなところで頑張るからそれが差として生まれます。
それに文法は文法問題を解くためだけにあるのではありません。文法は古文を正しく読むためにあるのです。
覚える量がたくさんあると言いましたが、これが覚えられたら、あとはパズルのように当てはめていくだけになります。
ここの頑張りは確実に報われます。コスパいいので諦めずに基礎固めを!
古文の勉強法③時代背景
古文は日本の話ですが、常識は違うことがあります。今では「え!?」ということも昔だったら「当たり前だよ」ということがあります。
それを知っているだけで古文の世界に入りやすくなり、理解も深まります。
単語や文法ができても内容が分からない人は、背景知識を知れば読みやすくなります。
やたら出家をしたり、色んな役職があったり、儀式があったり、男の人が家に来るのを待っていたりしますが、それらには理由があり、知っていると場面が想像しやすくなります。
背景知識は古文の参考書や漫画などで学ぶと楽しんで知識を増やしていけますよ。
古文の勉強④読解
続いては読解になります。
単語や文法といった基礎が固まっていればだいたいの文章は読むことができます。
しかし、読めても内容が把握できないことがありますよね。そこを突破するのが読解になります。
読解のカギは「主語」
単語や文法が出来ていても内容がよく分からないのには理由があります。それは「主語が分からなくなるから」です。
古文の厄介なところは主語を省略されていることです。そのせいで誰の動作か誰が話したのか、誰が思ったのかを見失ってしまうのです。
読解の1番のポイントは「主語を見失わないこと」にあります。常に動詞があったら「だれが」を補うようにしてみてください。
名前が出たらすぐに〇や◇で囲むのがおすすめです。
「だれが」が補えない時は敬語、格助詞、接続助詞などが重要になります。
詳しくは別の記事にまとめますが、昔の人が特に困らずに読めたのだから、苦手な人も訓練をすれば必ず読めるようになります。
読解力を鍛える方法
読解力を鍛えるには、学校で扱う文や問題集の文で主語を補いながら読むこと、誰に対しての敬語か補う、品詞分解をして単語や助動詞の訳を書くことで鍛えられます。
最初はめんどくさいかもしれませんが、実際に文を読みながらでないと、覚えた単語や文法が使いこなせるのかが判断できません。
暗記しても使えなかったら努力が無駄になってしまいます。
1文とかじゃなくて全文を読んで正しく意味を理解できるのか、読解力を付けていきましょう。
読解力は主語の補い、敬意の対象、品詞分解によってついてきます。
古文の勉強法⑤解き方
ここまでできたら最後は解き方です。古文には解き方があります。
と言っても単語、文法、時代背景、読解ができればほぼ問題ないです。
解き方として「リード文を読む」「問題文を読む」というものがあります。
リード文を読む
リード文には本文の助けになる貴重な情報が詰め込まれています。
登場人物が誰か、その登場人物たちの関係性は?何をしている場面?など書かれています。大ヒントです。
この情報があると読みやすくなるので必ず最初に見るようにしましょう。
問題文を読む
問題文を読むことも、ものすごくおすすめです。なぜなら「~①とあるがどうしてAはこのように思ったのか」など主語が書かれていることがあります。
古文の読みづらくなる原因は「主語を見失うことにある」と伝えましたが、問題文によって補えてしまうのです。
また選択肢を読むのもありです。
選択肢の1つは答えになるので、「あれ?どういうことだろう…」と内容がしっくりこない時に選択肢によって解決されることもあります。
馬鹿正直に本文を読むことはありません。解き方も身につけることで成績も上げることができます。
何から始めればいい?
では最後に、今のあなたは何から始めればいいのかまとめていきます。下の表を参考にしてください。
| 古文の勉強 何をするべきか | |
| 全く読めない人 | 単語の勉強 |
| 単語はわかるけど内容が分からない人 | 文法+問題集を時間決めずに解く |
| 単語や文法は一通りできる人 | 問題集で主語や単語助動詞の意味を書き込みながら解く |
| 問題も解ける人 | 時代背景+志望校の過去問を時間を測って解く |
これが今必要な勉強になります。自分の現状を把握して勉強を進めてください。
古文の勉強法のまとめ
さて、今回は大学受験に向けた古文の勉強法をまとめました。
古文はほとんどの受験生に必要になる教科です。ですが、めんどくさいと思って十分に勉強しない人もいるでしょう。
古文は単語、文法、時代背景、読解、解き方が分かればどんなタイプの文章でも理解できるようになります。
効率的に成績を伸ばしたい人は、単語&文法⇒時代背景⇒読解⇒解き方の順番で鍛えていきましょう。
古文を得点源に変えられるといいですね。
最後まで読んでくださってありがとうございました。